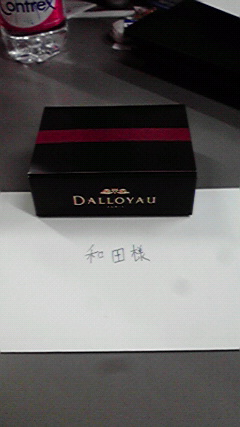2011.04.26
4月21日、上田市の中心地に長野県内最大級のショッピングモール「アリオ上田」がオープンしました。
イトーヨーカドーを中核として66の専門店からなるこのショッピングセンターには、8スクリーンからなるシネコン「TOHOシネマズ」も併設されています。
上田市近郊に住む映画ファンには嬉しいニュースです。
しかしその陰で、私が幼い頃から慣れしんできた映画館が3館、その長い歴史に幕を閉じます。
その3つは系列館ですが、どの小屋(あえてそう呼ばせて頂きます)も私の心に残るたくさんの名画をこれまで上映してきました。
ここで初めて観た映画は小学校5年生の時の「タワーリング・インフェルノ」。
同じく今でも大好きな「ポセイドン・アドベンチャー」に続くパニック・スペクタクル映画として父にせがんで連れて行ってもらい、2時間45分の間、大興奮したことを覚えています。
そして高校を卒業して東京へ行くまで、そして20代後半で上田に帰ってきてからも、古くからの味わいを持つこれらの映画館が大好きで、時間が空くと通い詰めました。
子供たちと観に行ったジブリの名作の数々。
あまりの衝撃にしばし席から立てなかった「セブン」。
真冬に暖房が弱くてガタガタ震えながらも心はポカポカと暖かかった竹中直人の「東京日和」。
ゴールデンウイークの真っ只中、たったひとりの観客だった「ロッキー・ザ・ファイナル」・・・。
数えればキリがありません。
そして私がこれらの小屋で最後に観た1本、それは若松孝二監督の「キャタピラー」でした。
奇しくもこの日も観客は私ひとりだけで、この秀作がひっそりと上映されている不幸をひとり嘆いたものでした。
ちなみにこの3館の中で一番大きな映画館(とはいってもわずか300席程ですが)は、200円追加で払うと2階で観ることができました。
ここはいつも貸切状態で、その最前列に座ってノビノビと映画を観るのが常でした。
中学や高校の頃は映画館の前で、上映中のポスターと少ない財布の中身とを見比べながら、意を決して窓口に向かったものでした。
そして身を削った代金と引き換えに、初めてその映画と対等に向かい合える気になりました。
極めて個人的な意見ですが、映画でも本でも、私は身銭を切る事が大切だと思っています。
ちなみに私は今の映画館の、全席指定というシステムが苦手です。
自分が好きなポジションがありますし、館内を見渡しながらうろうろと自分の席を見つけることも映画を楽しむ大切な導入部だと、今でも思っているからです。
余談ですが、若い頃初めて「全席指定」に座ったのは、東京の有楽座での「地獄の黙示録」でした。
S席が2500円、A席が2200円だったと思います。
お金がなかった私はもちろんA席で、そこは2階後方の席でした。
監督のコッポラが「この作品はフイルムオペラである」という考えから、この有楽座で上映されるフイルムだけクレジットなし、しかも結末が違うというスペシャルバージョンでロングランされました。
正直、ラストシーンは難解すぎて当時はさっぱり理解できませんでしたが、それから何度も観返し、今は私のベストテンに入る1本となっています。
閑話休題。
そんな古くからの面影を残す上田の映画館が3つ、間もなく姿を消します。
そして惜別の思いと共に振り返る時、私は「映画を観る」という行為と同じくらい「映画館に通う」という行為が好きだということに、改めて気付かされるのです。
上田映劇、そして上田デンキ館1・2、たくさんの思い出を今までありがとう。